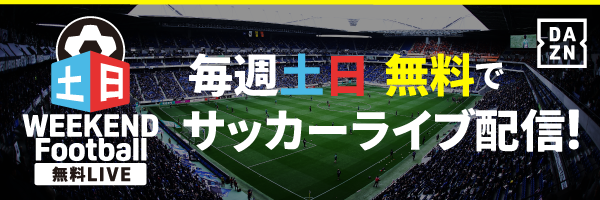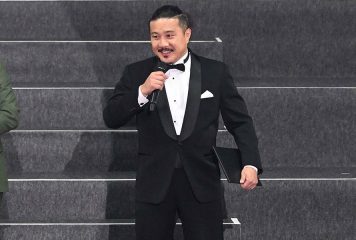期待高まる森保Jの大胆選考…有望な国内フレッシュ人材は? 「Jリーグで活躍」だけではない条件【コラム】

国内組の編成が予想される7月のE-1選手権、森保監督が語る選考のポイント
2026年北中米ワールドカップ(W杯)出場が決定し、1年2か月後の本番に向けての強化が本格化する日本代表。次の代表活動は6月に控えるW杯アジア最終予選のオーストラリア&インドネシア2連戦だ。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
ここは数少ないインターナショナルマッチデー(IMD)の1つ。欧州組を招集できる貴重なチャンスであるうえ、本大会ドローのポット分けに関わるFIFAポイントも高い。ゆえに、森保一監督は基本的に最終予選の主軸を中心とした編成で挑むはず。新たなメンバーを試すにしても、26人中の5~6人程度にとどめるのではないか。
新戦力テストの場という意味では、翌7月のE-1選手権(韓国)のほうがより重要度が高い。この大会はIMDではないため、基本的には拘束力がなく欧州組を招集できない。欧州もプレシーズンの時期のため、クラブ側が合流の遅れを容認してくれる選手に限っては呼べる可能性もあるが、かなり限定的になると見られる。大半のメンバーは国内組から選出されることになると言っていい。
「E-1に連れていく選手は来年のW杯につながるかどうかが一番の選考ポイント。そのうえで、実力的に同等の選手が複数いれば、若い選手を選ぶことになると思います」と、森保監督は4月6日の柏レイソル対ガンバ大阪戦を視察した際に語っていた。ただ、今もなおベストな方向性を定め切れずに苦慮している様子だ。
E-1選手権は確かに位置づけが難しい大会ではある。2003年に第1回の日本大会がスタートした頃はまだ欧州組が少なかったため、日本代表の主力級をズラリと並べることができたが、時代の流れとともにそういうことができなくなってきたからだ。
2010年代以降を振り返ってみると、ザックジャパン時代の2013年韓国大会はA代表経験のなかった柿谷曜一朗、大迫勇也(ヴィッセル神戸)、山口蛍(V・ファーレン長崎)ら若手を多数招集。彼らと2014年ブラジルW杯アジア最終予選参戦組の駒野友一(サンフレッチェ広島ユースコーチ)、栗原勇蔵(横浜F・マリノス強化担当)、西川周作(浦和レッズ)らを融合させた編成で挑み、決勝で韓国を撃破。2005年韓国大会以来、2度目のタイトルを獲得している。
加えて言うと、同大会で異彩を放った柿谷、山口、大迫、森重真人(FC東京)、青山敏弘(広島コーチ)、齋藤学(アスルクラロ沼津)とGKの西川、権田修一(デプレツェニ)の8人が本大会メンバー入り。彼らの全員がブラジルW杯で結果を出したとは言い難い部分もあったが、次世代を担うタレント発掘という意味では大きな成果があった。
人材発掘で効果があったE-1選手権、「Jリーグで活躍」以外に重視すべきテーマ
一方、バヒド・ハリルホジッチ監督が率いた2015年中国大会と2017年中国大会に目を向けると、いずれも「代表常連の国内組+ポテンシャルを秘めた若手」という印象が強かった。
前者は槙野智章、宇佐美貴史(ガンバ大阪)らに谷口彰悟(シント=トロイデン)、遠藤航(リバプール)らを加えた編成。後者はベテランの今野泰幸(南葛SC)、小林悠(川崎フロンターレ)、倉田秋(G大阪)、2018年ロシアW杯最終予選を戦った昌子源(FC町田ゼルビア)、井手口陽介(神戸)、売り出し中の若手だった伊東純也(スタッド・ランス)といったより幅広い陣容でチームを作って戦った。結果的にはどちらもタイトルを逃し、低調な戦いに終始したが、のちの代表主軸となる遠藤や伊東を発掘したという意味では有益だったのではないか。
こうした過去の変遷を踏まえ、森保監督は2019年韓国大会、2022年日本大会で明確なテーマを設定した。
まず2019年大会は「東京五輪・2022年カタールW杯に向けた若手の底上げの場」。大迫敬介(広島)、橋岡大樹(ルートン・タウン)、相馬勇紀(町田)、田中碧(リーズ)、小川航基(NECナイメンヘン)、上田綺世(フェイエノールト)らを抜擢。韓国に及ばず準優勝に終わったが、彼らの成長には確実に寄与している。
そして2022年大会はW杯4か月前という押し迫った時期の開催だったこともあり、「カタールW杯につながりそうな人材の最終テスト」と位置づけた。その中から谷口、山根視来(LAギャラクシー)、相馬、町野修斗(キール)の4人が最終メンバーに滑り込んでおり、特に国内組だった谷口の躍進は目覚ましいものがあった。
こうした流れを踏まえると、やはり今夏のE-1も明確なテーマ設定をしてから人選を進めていったほうがいい。単に「Jリーグで活躍している」というだけでなく、「本当に1年後のW杯で戦力になる人材か」「2026年W杯以降に代表になりそうな選手なのか」に主眼を置き、しっかりと見定めて選ぶべきだ。
欧州→国内復帰組の行方は? フレッシュ人材が秘めているプラス要素
昨今のJリーグは欧州から戻ってきて活躍する年長者も少なくない。今季J1得点ランキング上位の北川航也(清水エスパルス)、西村拓真(町田)、鈴木優磨(鹿島アントラーズ)などは揃って国内復帰組。年齢的に間もなく30歳ということで、先々を見据えると少し難しい印象もある。
となれば、同じ得点上位グループでも、20歳の北野颯太(セレッソ大阪)。24歳の福田翔生と21歳の鈴木章斗(ともに湘南ベルマーレ)といった将来性のあるフレッシュな人材を選んで、国際経験を積ませたほうがプラス要素は多いだろう。
ほかのポジションに関しても、現時点でアシストランク首位タイの24歳の三浦颯太(川崎フロンターレ)、デュエル勝率2位の21歳・鈴木淳之介(湘南)、3位の24歳・綱島悠斗(東京ヴェルディ)、走行距離4位の24歳・熊坂光希(柏)などは明らかに有望株。彼らのような20代前半のタレントを積極的に選んだほうが日本代表の活性化にもつながるかもしれない。
2026年W杯の1年前というタイミングを踏まえても、ザックジャパンで臨んだ2013年大会のように若手がブレイクしてくれれば理想的。森保監督には大胆な選手選考を期待したい。
2019年大会の指揮官は実際にそうしたトライをし、結果が出ずに批判を受け、当時は解任論も少なからず出た。本人にしてみれば、当時の思いが脳裏をかすめるだろうが、やはり今の日本代表をもう一段階引き上げるためには若い力の台頭が不可欠だ。それを推し進める意味でE-1選手権は格好の場。今回はポテンシャル重視の選考でチーム編成を進めてもらいたいところ。その方向性がどういったものになるのか。今後の成り行きを慎重に見守っていきたい。

元川悦子
もとかわ・えつこ/1967年、長野県松本市生まれ。千葉大学法経学部卒業後、業界紙、夕刊紙記者を経て、94年からフリーに転身。サッカーの取材を始める。日本代表は97年から本格的に追い始め、練習は非公開でも通って選手のコメントを取り、アウェー戦もほぼ現地取材。ワールドカップは94年アメリカ大会から8回連続で現地へ赴いた。近年はほかのスポーツや経済界などで活躍する人物のドキュメンタリー取材も手掛ける。著書に「僕らがサッカーボーイズだった頃1~4」(カンゼン)など。