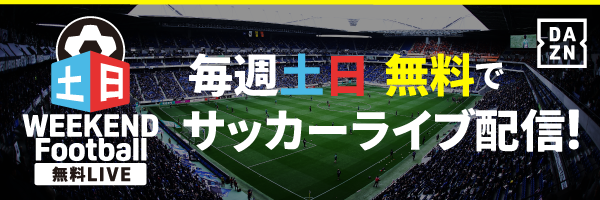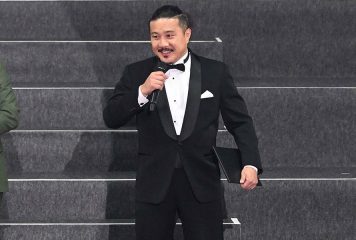Jリーグの歓喜と悪夢…劇的ドラマを生む「8%」 何が起こるか分からない悲劇の教訓【コラム】

今季J1全ゴール中、後半アディショナルタイムに17点のドラマ
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
Jリーグでは劇的な試合が続いている。例えば川崎フロンターレvs横浜F・マリノス、3-3の熱戦がそうだった。
2-1と川崎リードで迎えた後半44分、最後の力を振り絞って右サイドバックの宮市亮が駆け上がると、植中朝日がジャンピングボレー。このボールを天野純が押し込んでまず同点。さらに左からのクロスからもつれ、最後はヤン・マテウスが蹴り込んで横浜FMが逆転する。しかし後半アディショナルタイム10分、脇坂泰斗のCKを日本代表の20歳、高井幸大がヘディングで決めて、最後の最後で同点とした。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
劇的なゴールと言えばセレッソ大阪vs鹿島アントラーズのゴールも後半アディショナルタイム12分。それまで2回のVAR(ビデオ・アシスタント・レフェリー)介入も含めて5回ゴールが決まらず、後半アディショナルタイム11分のPKは鹿島GK早川友基に止められていたC大阪が、CKからの混戦を進藤亮佑が決めて決勝点とした。
今シーズンのJ1リーグは第10節を終えて全部で210ゴールが生まれた。そのうち後半アディショナルタイムでの得点は17点。約8%を占める。ちなみに、2024年はJ1リーグで全1013点が生まれており、そのうち後半アディショナルタイムでの得点は88点。約9%を占めており、2023年は全777ゴールのうちに71得点、約9%だった。
それだけ試合が最後までどうなるか分からないという展開は、見ているほうにとって楽しいものだろう。日本代表の森保一監督は「サッカーは何が起こるか分からないことであったり、逆に言えば最後まで諦めないっていう姿勢で戦うことが大切」「終了間際まで勝敗がどうなるか分からないというエキサイティングの試合ばかりで、Jリーグの魅力が上がってきているということをすごく感じています」と感想を述べている。
一方で、失点の8~9%は後半アディショナルタイムに生まれている、と考え方を変えてみるとどうだろう。しっかりと試合を終わらせられないと見ることもできるのではないか。それは昔から変わらない日本の弱点ではないだろうか。
日本サッカー史に刻まれた「後半アディショナルタイムの悲劇」
1993年10月28日、日本代表はドーハにいた。1994年アメリカ・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選はカタールでの集中開催で、その日は最終戦だった。初戦でサウジアラビアに引き分け、2戦目はイランに敗戦。3戦目で朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を下し、4戦目の韓国にも勝利を収めた。
イラクとの最終戦を前に日本はグループトップ。引き分けでも他会場の結果次第ではW杯初出場が決まるという試合を迎える。そのイラク戦、日本は三浦知良のゴールで幸先良く先制し、前半を1-0で終える。後半、一度は同点にされるものの中山雅史が得点して2-1とリードし、後半アディショナルタイム(当時はロスタイム)を迎えた。
その最後のCKで日本はヘディングシュートを決められ、同点にされる。そして韓国に逆転され、日本はW杯に出場することができなかった。それが「ドーハの悲劇」と言われる試合だ。そのイラク戦に出場停止明けから戻って先発に入っていたのが選手時代の森保監督だった。
あの時、日本は試合の終わらせ方を学ばなければいけないと思ったはずだ。当時のJリーグはリーグ戦でもすべての試合で決着を付けるべく、延長戦でゴールが入った瞬間に試合が終わる「Vゴール」やPK戦が採用されていた。
そのため最後に守備的になって終わらせるというのができないのではないかという批判もあった(もっともW杯初出場を決めた「ジョホールバルの歓喜」は「ゴールデン(V)ゴール」方式だったので、むしろ続けて良かったのかもしれないのだが、それはまた別の話)。
日本はまだ試合の終わらせ方を知らないのか――日本代表・森保監督の回答は?
日本はまだ試合の終わらせ方を知らないのだろうか。そう森保監督に聞いてみた。
「追い付かれた側からすれば、なぜ追い付かれたのかを考える意味では、追い付かれ方も守りに入ってしまってやられたのか、最後勝ち切りにいってやられるのかは違うと思いますし、いろんな要因があると思います。ただ、私自身の話で言うと、ドーハの経験は、守りだけに入ってしまった、それが結局守ることにはつながらなかったっていうところは、やはりボールを奪いに行くとか、攻めの守り、攻める意識を持たないといけないというのは、私自身の学びの中ではドーハの経験を生かしているとところはあります。なかなか結果が出ていないチームは、最後勝ち切るために硬くなってしまうところはある印象を持っています」
後半アディショナルタイムに勝敗を決するゴールが決まると、どうしても得点を上げたほうに目が行ってしまう。それは報じる立場としての反省点でもある。だが「なぜあそこでしっかり逃げ切れなかったのか」という点を忘れずに追求しなければ、またあの悪夢が蘇ってしまうかもしれない。
今は「最後に点を取る」立場になったように思える日本だが、「最後に点を取られた」ことは忘れてはならない。あの厳しい教訓がその後の日本を作ってきたのだから。今週のコラムは自戒を込めて書き残す内容になった。

森 雅史
もり・まさふみ/佐賀県出身。週刊専門誌を皮切りにサッカーを専門分野として数多くの雑誌・書籍に携わる。ロングスパンの丁寧な取材とインタビューを得意とし、取材対象も選手やチームスタッフにとどまらず幅広くカバー。2009年に本格的に独立し、11年には朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の平壌で開催された日本代表戦を取材した。「日本蹴球合同会社」の代表を務め、「みんなのごはん」「J論プレミアム」などで連載中。