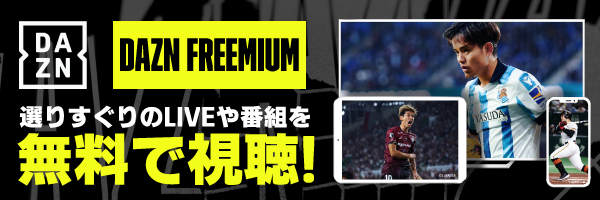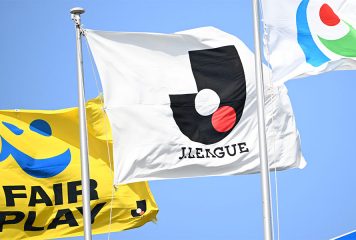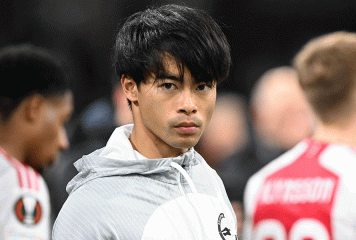選手目線で見たJリーグ「秋春制」 元日本代表FWが語るメリット・デメリット「それが一番怖い」【インタビュー】

Jリーグの秋春制を歓迎する岡崎「選手にとってかなりありがたいと感じます」
「日本サッカーの未来を考える」を新コンセプトに掲げる「FOOTBALL ZONE」では、現場の声を重視しながら日本サッカー界のあるべき姿を模索していく。Jリーグと欧州リーグで長年プレーし、現在ドイツ6部チームで指揮を執る元日本代表FW岡崎慎司は、Jリーグの「秋春制移行」について選手視点のメリットを挙げつつ、「移行になった時、何ができるかを考えることが大事だと思っている」と持論を展開している。(取材・文=中野吉之伴)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
Jリーグは2026-27シーズンから秋春制への移行を発表している。2025シーズンが終わったあと半期の特別大会を経て、2026年8月にシーズン開幕。12月半ばから2月の終わりを目処にウィンターブレイクを取り、2027年5月にシーズン終了となる予定だ。Jリーグをさらに世界へつなげるために実施される大きな変革の1つだろう。とはいえ、さまざまな賛否両論がある変革でもある。
シーズン移行は選手に何をもたらすのか。現役時代、欧州で13シーズン戦った岡崎慎司の見解を尋ねてみた。
「選手だった時の感覚だと、シーズンを合わせてもらえると、例えばシーズンオフが一緒なので会いたい人に会いやすくなるというのがあると思います。日本の選手とヨーロッパでプレーしている日本人選手が交流しやすいし、休みのタイミングも合う。スタッフや関係者ともそうですね。シンプルにそういう側面があるし、これは選手にとってかなりありがたいと感じます」
チーム合流がしやすくなる点も岡崎はメリットに挙げる。ヨーロッパにおいてシーズン途中にあたる冬の移籍はチーム事情によるところが多い。そのためピンポイントで即戦力として獲得された選手は比較的優先して起用される可能性は高い。岡崎もそのパターンだった。
「僕も冬からの移籍でしたね。僕の場合は休みがない状態で、しかもアジアカップが終わってそのまま参加したのでテンション的にフレッシュな状態で入れたんですね。周りは残留争いでいろいろ疲れているなか、俺はやる気に満ちて入れたのでパワーを出せたし、そういう意味では残留に貢献できたのもあった」
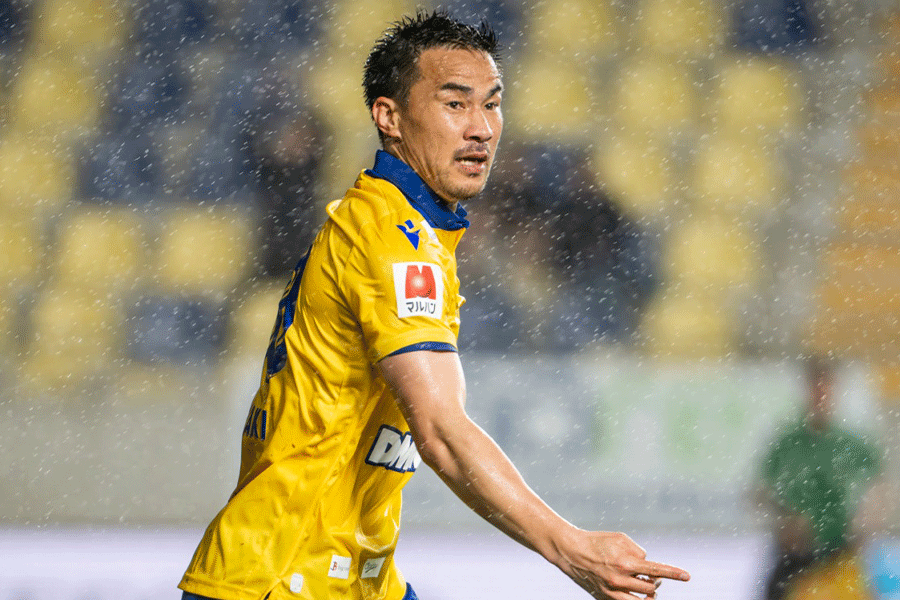
「僕はどっちでもいい」と語る岡崎の真意…大事なのは「何ができるか」
ただし冬の移籍で上手くハマらないと、すぐに構想外へと追いやられるリスクも小さくない。特に語学や文化の面で違いが大きい地域から来た選手は、順応するための時間が欧州圏からの移籍に比べてどうしても必要となるが、ギリギリの残留争いや欧州カップ戦出場権を戦うような場合、そうした選手の個別事情に配慮するのは難しい。
「そうなんですよね。だからプレシーズンに参加して開幕に向けてコミュニケーションを重ねて一緒に準備するほうがいいことだと思う。シーズンを通した選手のパフォーマンスを考えると、間違いなくそっちのほうがいいですね」
コンディション面やスケジュール面の要素が今のままでも移籍は成立するし、そこで順応できる選手もいる。だがズレがあったままチームに合流することで、最初は無理が利いてもどこかで身体や精神的な疲れが出て、パフォーマンスが落ちてしまうリスクもはらんでいる。
「だから」と言って岡崎が少し考え、そして「僕はどっちでもいいと思うんですよ」と言葉をつなげた。その真意は?
「どっちがいいかではなくて、シーズン移行になった時に何ができるかを考えることが大事だと思っているんです。例えばシーズンを合わせることで夏のプレシーズン序盤に練習参加させやすくなりますよね。最初はまだ代表選手が集まっていないから参加しやすい。じゃあその時期を上手く生かして、将来性のある若手が参加できる機会を作って、向こうでどんどん見させる。『お、こいつ結構面白いじゃないか』ってなればチェックしておいてもらえる。
何ができるかを今から考えていかないといけない。いろんなことを予測して、日本クラブが先手を打てるようにしなきゃいけない。シーズン移行で全てがやりやすくなるという感覚になると後手になる。それが一番怖いなって思います。ヨーロッパは動くのが早いので、日本がシーズン移行する情報が入ったらすぐに考えて準備を始める。『これができるな、あれができるな』という戦略を考える。日本からスポンサーを獲得するためにマーケティングして仕掛けてくると思うんです。逆に日本側は、この変革を生かしてヨーロッパと何ができるかを考え、準備しておかないといけない」
鍵は長期的な視野と逆算のステップ「1つ決めたからすべてがOKにはならない」
スケジュール的にもヨーロッパと似通ってくる。これまでは違うからこそ生まれていたメリットの部分もあったが、それがなくなる。土俵が同じなかでクラブ間の交渉や仕掛け合いがよりオープンとなる。
「マーケティング、おそらく日本が苦手とする『勝負』のところで試されるんじゃないですか? 僕は常に疑問を持つべきだと思っているんです。さっきも言ったけど、何か1つ決めたからってすべてがOKにはならない。長期的な視野を持って、じゃあ移行するのであればそのメリットを最大限に生かすためにどんな準備やサポートが必要なのかを明確にしていくことが大事。もちろんJリーグや各クラブもいろいろ考えて動いていると思います。そんななかで例えば雪国支援として5年、10年かけてこういうことをやっていきますというビジョンを出して、支援体制も整えていく。そうやって先を見据えてみんなで考えて動いていくことが必要だと思います」
欧州に長くいるからこその大事な指摘。メリットとデメリットは表裏一体。できないからやらないではなくて、どうすればできるのか、どうすればメリットになるのかを考える。欧州であれば芝下暖房があり、降雪時でも試合ができる。あるいはスタジアムに雪対策の屋根をつけたり、観客席下にオイルヒーターを巡らせて暖房効果を持たせたり、スタジアムへの移動をより快適にするためにシャトルバス以外に路面電車というのを街計画に合わせて導入したりできるかもしれない。最寄り駅からスタジアムまでにアーケードを作り、雨や雪でも快適に行けたら素晴らしいことだ。
どのような未来像を描き、そのためにどんなステップを踏むべきかの議論へつなげていく。長期的な視野からの逆算がより明確に見えてきた時に初めて、シーズン移行はポジティブな分岐点となるのだろう。
(中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano)

中野吉之伴
なかの・きちのすけ/1977年生まれ。ドイツ・フライブルク在住のサッカー育成指導者。グラスルーツの育成エキスパートになるべく渡独し、ドイツサッカー協会公認A級ライセンス(UEFA-Aレベル)取得。SCフライブルクU-15で研修を積み、地域に密着したドイツのさまざまなクラブで20年以上の育成・指導者キャリアを持つ。育成・指導者関連の記事を多数執筆するほか、ブンデスリーガをはじめ周辺諸国で精力的に取材。著書に『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』(ナツメ社)、『世界王者ドイツ年代別トレーニングの教科書』(カンゼン)。