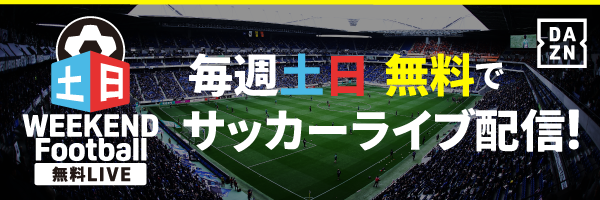日本代表の「W杯ベスト8」は現実的か? “スーパータレント”はいなくても…【コラム】

多様性が増している日本代表、幅広いプレースタイルに見る大きな変化
日本代表はアジア予選を難なく通過し、ここからワールドカップ(W杯)本大会への準備になる。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
米国、カナダ、メキシコの共同開催となる2026年W杯は48チームに拡大。4チームによるグループステージはこれまでと同じだが、ノックアウトステージがラウンド32から始まる。
日本代表はまだノックアウトステージで勝ったことがない。今までなら1つ勝てばベスト8だったが、それが2つ勝たないとベスト8に到達できないわけで、組み合わせ次第ではかなり高いハードルになってしまうかもしれない。
一方、48チームになったことでグループステージは今までほど強豪と当たらないで済む可能性もある。3位でも成績上位の8チームは次のラウンドに進めるので、その点はいくぶん楽になるだろう。
そこで問われるのが対応力だ。
前回大会のドイツ、スペイン、クロアチアとの試合のように相手にボールを持たれる展開ばかりではなく、コスタリカ戦のように日本が保持して攻め込む試合も多くなると想定される。守備的、攻撃的のどちらの流れになっても力を発揮できることが重要だ。
日本代表はもともと均質的なチームである。欧州や南米のような多様性は乏しい。欧州は多様性が増したことで対応力が上がったチームが多く、フランスやベルギーはその典型だが、ドイツやイングランドも多様性のメリットを享受している。いろいろなタイプの選手がいるのでプレースタイルに幅をつけることができた。
欧州で均質的なチームとしてスウェーデンがあった。現在は違っているが、2018年ロシア大会時点ではそうだった。中米のメキシコも均質的だ。均質的なチームは1つのプレースタイルに特化していて長所短所がはっきりしているので、対戦相手との相性に左右されやすい。日本もそうだったのだが、近年は変化が出てきた。
GK鈴木彩艶、センターバックの冨安健洋や板倉滉など、長身でフィジカル能力の高い選手が現れ、均質的な中にも多様性が増した。戦術的にもカタールW杯の守備的な戦い方から、今回のアジア予選の超攻撃布陣まで、幅広いプレーができつつある。スーパースターはいないけれども、それに準ずる選手が多い。軸になる選手はいるとしても、ある程度は誰が出ても、あるいはどんな戦い方でも一定水準をキープできるようになっている。
サイドアタッカーとして伊東純也、久保建英、三笘薫、中村敬斗がいて、それぞれ特徴が違っている。センターフォワードの上田綺世、小川航基、古橋亨梧、前田大然もしかり。キリアン・ムバッペやリオネル・メッシのように相手がどうでも関係ないスーパータレントではないが、相性が良ければ力を発揮できるアタッカーを複数持っている。均質的ではあるけれどもタイプの違いはあり、全体のレベルが高い。こうした人材を上手く活用すれば対応力はかなり期待できそうである。
すでに下地はできているので、これから本大会までの間にスムーズな運用ができるようしておくことで、ベスト8は現実的になってくるのではないか。
(西部謙司 / Kenji Nishibe)

西部謙司
にしべ・けんじ/1962年生まれ、東京都出身。サッカー専門誌の編集記者を経て、2002年からフリーランスとして活動。1995年から98年までパリに在住し、欧州サッカーを中心に取材した。戦術分析に定評があり、『サッカー日本代表戦術アナライズ』(カンゼン)、『戦術リストランテ』(ソル・メディア)など著書多数。またJリーグでは長年ジェフユナイテッド千葉を追っており、ウェブマガジン『犬の生活SUPER』(https://www.targma.jp/nishibemag/)を配信している。