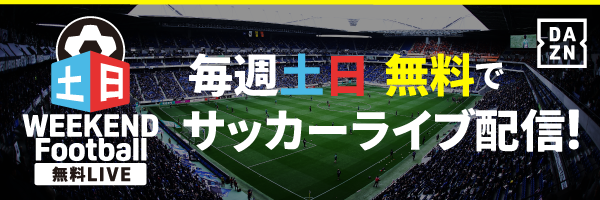「全国で試したい」…未来につながる日本サッカー改革 岡崎慎司の願い「一石四鳥五鳥」【インタビュー】

雨水貯水の新システムを導入「これは日本にとって良い手段になると思います」
「日本サッカーの未来を考える」を新コンセプトに掲げる「FOOTBALL ZONE」では、現場の声を重視しながら日本サッカー界のあるべき姿を模索していく。現在ドイツ6部チームで指揮を執る元日本代表FW岡崎慎司は、日本サッカーの改善点として“未来につながるグラウンド”に注目。「一石四鳥五鳥ぐらいのシステム」に触れつつ、「日本全国で試したい」と情熱を燃やしている。(取材・文=中野吉之伴)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
日本のサッカー環境をさらに良くするために何ができるのか。元日本代表FWで現在はドイツ6部FCバサラ・マインツで監督を務める岡崎慎司が着目していることの1つが、未来を見据えたグラウンド作りだ。
岡崎がクラブ理事を務めるFCバサラ兵庫(関西1部)では、神戸市西区に「BASARA VILLAGE GREEN(バサラヴィレッジグリーン)」という練習拠点を2021年に完成させている。人工芝のサッカーコートだが、ほかのグラウンドと大きく違うのは日本で初めてとなるピッチ下に雨水を貯水できるシステムを導入している点だ。
「誤解されることもあるんですが、僕らは人工芝化を進めているわけではないんです。天然芝のほうがいいなと思っています。ただ、すべてを天然芝化するのはコストの面などでも難しい。とはいえ人工芝には問題もあります。例えば人工芝で使われるゴムチップが地球温暖化を加速させる理由の1つになっていると。僕らが導入したのは、そうしたことへの対策としてオランダで開発されたシステムなんです。人工芝をより良く、より環境に適した形で使うためのシステムをオランダの会社が作った。僕も実際に現地まで足を運んで挨拶に行ってきました。これは日本にとって良い手段になると思います」
貯めておいた雨水を蒸発させる際にクールダウンさせ、40%近く表面温度を低減できるという。自然現象の蒸発を利用するため電力は不要。素材には再利用プラスチックを使うなど環境にやさしい冷却システムとして注目を集めている。

「もはやグラウンドをただ作ろうっていうだけでは古い」と力説する訳
岡崎はさらにその先を考えている。
「日本全国で試したいんです。各地域において用途が変わってくるじゃないですか。僕らがやっているように雨水を貯めて、冷却システムとして使うのか。あるいは貯水して別の用途に使うのか。天然芝に近いグラウンドの感覚でサッカーをするために使うのか。そもそも貯水場としての機能で十分プラスに働くと考えることができる。温暖化に対して、これを広めていくことはメリットになるはず。サッカーだけじゃなくて、ほかのスポーツでも運用できる。コンクリートとかを使わず、全部リサイクルのものを使っていて、水をさまざまな形で再利用することができる。一石四鳥五鳥ぐらいのシステムだと思います。こういう活動がもっと増えるべきだと思いますね。
環境を良くするためには、行政を動かすことも必要になる。スポーツ環境が整っているドイツは1950年代に行政が最初に動いて、『スポーツ促進が国民の健康につながり、国の利益になる』という目的でスタートした。日本で今すぐ大規模に行うことはできないと思う。そうなるとスポーツやサッカーの力を知っている人のサポートが、より大事になってくる」
例えば全国有数の芝生の生産地である鳥取県では、J3のガイナーレ鳥取が芝生生産事業「Shibafull(しばふる)」を立ち上げ、クラブが持つ芝生生産のノウハウを地域に還元。校庭の芝生化を進めている。岡崎が言うように、地域に合った取り組みを考え、積極的に実行していくことが求められる。
日本は、ヨーロッパのようにどこにでも芝のグラウンドがあるという環境ではない。だが今だけを見て判断するのではなく、未来をポジティブに描くことができるかどうか。それが大事だと岡崎は主張する。
「日本は今から作っていく段階。だったらもっと新しいことができるということなんです。ただ作るだけじゃなく、その先を見据えて、ヨーロッパもまだやってないことを目指していく。もはやグラウンドをただ作ろうっていうだけでは古いんです。どんなグラウンドを、何のために、どんな意図で作るのか。僕らが取り入れた雨水を貯水するシステムはその1つで、そうしたものをもっと広めていくべきだと思っています。ほかにもっと適したシステムがあるならそれでもいい。『未来につながるグラウンド』なのかどうか。それは大事なテーマだと思う」
未来につながるグラウンドに込めた想い「スポーツをするだけの空間でなく…」
「未来につながるグラウンド」
ワクワクするフレーズだ。世界中でSDGs(持続可能な開発目標)問題が注目されている時代だからこそ、行政や企業との連携がこれまで以上に求められるし、これまで以上にチャレンジができるチャンスがあると言えるかもしれない。
FCバサラ兵庫のホームページには岡崎の思いが込められたメッセージがある。
「スポーツをするだけの空間でなく、気軽に人が集まり、地域の人と人をつなぐ空間にしていきたい。そして、美しい田園風景が広がる自然豊かな今の空間を守っていくためにも、スポーツを通じて持続可能な地域コミュニティを築いていきたい。そんな理想の空間を目指しております」
日本中にさまざまな「未来につながるグラウンド」が生まれるのは、決して夢物語ではないのかもしれない。
(中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano)

中野吉之伴
なかの・きちのすけ/1977年生まれ。ドイツ・フライブルク在住のサッカー育成指導者。グラスルーツの育成エキスパートになるべく渡独し、ドイツサッカー協会公認A級ライセンス(UEFA-Aレベル)取得。SCフライブルクU-15で研修を積み、地域に密着したドイツのさまざまなクラブで20年以上の育成・指導者キャリアを持つ。育成・指導者関連の記事を多数執筆するほか、ブンデスリーガをはじめ周辺諸国で精力的に取材。著書に『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』(ナツメ社)、『世界王者ドイツ年代別トレーニングの教科書』(カンゼン)。