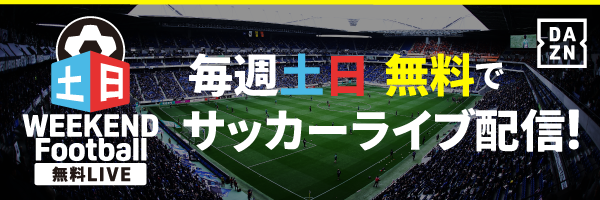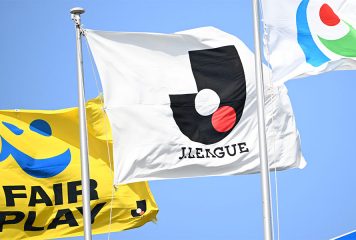日本サッカーの発展は「まずは環境かなと思うんです」 岡崎慎司が欧州で実感した”共通言語”としての役割【インタビュー】

海外で長年プレー、現在ドイツで指揮を執る岡崎が力説する「環境の良さ」
サッカー界のあるべき姿を模索していく。現在ドイツ6部チームで指揮を執る元日本代表FW岡崎慎司は、欧州で長年プレーした自身の経験を基に日本サッカー界の未来図について持論を展開し、「日本代表が強くなることがすべてじゃない。サッカーが文化になっていくっていうことが大事だと感じています」と語っている。(取材・文=中野吉之伴)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
「日本サッカーを共に盛り上げる」「日本サッカーの未来を共に考える」というテーマを編集部からもらった時、すぐ頭に浮かんだのが岡崎慎司だ。現役時代から自分のことだけではなく、日本サッカーが考えるべきこと、変わるべきところについて様々な視点で話をしてくれていたのを思い出す。きっと興味深い話がたくさん出てくるに違いない。インタビューを打診したらすぐに快諾してくれた。
岡崎が指揮を執るドイツ6部のFCバサラ・マインツが試合を終えた翌日、マインツ市内のカフェで話を伺った。
「今まで日本人選手としたらトップレベルのところでやっていたので、そこから見た景色で日本のサッカーっていうのを考えたりはしていたんですけど、やっぱり環境が変われば考えることも変わるなと。今、マインツで指導者としてこの地域のサッカーで揉まれているなか、環境の良さに改めて気付かされます。子供たちがのびのびサッカーする場がたくさんある。やろうと思ったら、土日の朝とかもグラウンドに来てサッカーができる。日本代表が強くなることがすべてじゃない。2050年までにワールドカップで優勝すると日本サッカー協会が掲げているのも、もちろん大事だと思う。その一方で、ドイツやスペインでの生活を経験していると、サッカーが文化になっていくっていうことが大事だなと感じています」
ヨーロッパではサッカーが文化という話はよく聞く。では具体的に岡崎はどんなところに「あぁ、サッカーが文化になっている」と感じるのだろうか。「ちょっと抽象的かもしれないですけど……」と前置きしてから話し始めた。
「それがないと国が成り立たない、今この国の人たちがサッカーを奪われたらどうなるんだろうというぐらいの重さがある。日本だと、なくなったらサッカーファンは困るかもしれないけど、世間的に多くの人たちが困るほどではないかもしれない。コロナ禍の頃も、サッカーが再開されたのはやっぱりヨーロッパが一番早かった。サッカーが最初に動き出して、経済が回り出したっていうのがある。ドイツやスペインだと娯楽がないって言う日本の人もいるけど、サッカーがあることが何より大事で、何もないわけないんです。あとスポーツがあることでみんなが健康的になれたり、家族との絆が生まれたりする。スポーツがあることで、みんなの生活レベルが少しずつでも充実していく。もちろん日本でも同じだけど、そういう人の割合が圧倒的に多いのがヨーロッパなのかなって」

欧州でサッカーは1つの共通言語「サッカーをやっていれば仲良くなれる」
欧州だとサッカーは1つの共通言語のような意味合いを持っている。サッカーがどういうスポーツなのか、というのを本当に多くの人が知っている。そしてサッカーを全く分からない人に対して、どう説明したらいいかを知っている人も多い。先日スタジアムでブンデスリーガを観戦した時、近くで年配の母親にサッカーの説明をしている男性がいたが、分かりやすく丁寧に話をしていたのがとても印象的だった。
「互いにゴールを狙ってゴールを守るために、グラウンドでスペースをどのように攻略するかを考えて、配置や動きを考えるんだ。ボールを持った選手からゴールまでのルートは相手チームも注意して守るし、人が多く配置されているからシュートに持ち込むのが難しい。さっきみたいに選手がタイミング良く動いて相手をずらすことができたら、ボールを送れるコースが生まれたりするでしょ? そうするとチャンスにつながりやすいんだよ」
その母親は頷きながらそんな話を聞いて、「さっきの場面はなんで上手くいかなかったの?」「あ、今あそこのコースが空いていたと思うけど?」と息子に質問し、それにまた答えてというサッカー談義が自然とできているのは素敵なことだ。
「本当にそうですね。サッカーを通じて仕事をしたり、知り合いとつながったり、子供の世界でもそうだと思います。サッカーをやっていれば仲良くなれる」(岡崎)
ドイツでは社会環境の変化により、昔ほどストリートサッカーを行う子供があちこちにいるという時代ではなくなってきた。だが、まったくいなくなったわけではない。ミニサッカーコートが街の様々な場所にあり、そこには今も変わらず子供や大人が一緒になってサッカーを楽しむ環境があるのだ。
日本では、公園で自主練をしているグループがいくつかあっても、そこから自然発生的にミニゲームに発展するという状況にはなりにくい。各自がリフティングやドリブル、シュート練習などをして終わる。サッカーはつながりのスポーツだ。自主練から、2対2や3対3の練習ができたら楽しいだろうし、5対5ならより夢中になるミニゲームもできるだろう。
岡崎が説く環境作りの重要性「Jリーグを盛り上げるのは大事だけど…」
最後に岡崎も環境作りの重要性を説いた。
「そうです。公園でボールを蹴っている子供たちが自然発生的にゲームをできるようになるには、まずは環境かなと思うんです。まずそこに集まるスペースを作ること。日本には集まれる場所が少ない。だから逆算する。その集まるスペースを作るには行政の協力が必要になってくる。
例えばJリーグを盛り上げるのは大事だけど、Jリーグさえ盛り上がればいい、クラブに関わる人たちだけが良ければいいっていう考えだけになってしまうのは良くないですよね。Jリーグも一緒になって、もっともっと地域と結びついて、こういう環境作りをしていくことが大事だと思います。そうやってスポーツを充実させることでヨーロッパとのつながりも、もっと深くなるような気がするんです。
日本代表だけではなくて、それに伴ってこうしたところの活動もしていかないといけないし、継続的にやっていかないといけない。ドイツやスペインなどがワールドカップで優勝したのを見ていると、もっとサッカーが根付くためにどうしたらいいかっていうのを考えていくのが大事だし、そのための環境をどう作っていくのかもすごく大事という思いですね」
(中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano)

中野吉之伴
なかの・きちのすけ/1977年生まれ。ドイツ・フライブルク在住のサッカー育成指導者。グラスルーツの育成エキスパートになるべく渡独し、ドイツサッカー協会公認A級ライセンス(UEFA-Aレベル)取得。SCフライブルクU-15で研修を積み、地域に密着したドイツのさまざまなクラブで20年以上の育成・指導者キャリアを持つ。育成・指導者関連の記事を多数執筆するほか、ブンデスリーガをはじめ周辺諸国で精力的に取材。著書に『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』(ナツメ社)、『世界王者ドイツ年代別トレーニングの教科書』(カンゼン)。