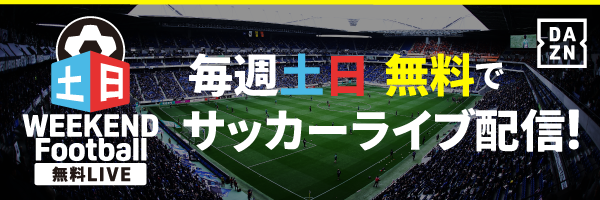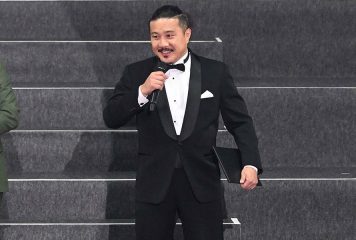- HOME
- 今日のピックアップ記事
- 日本の「ごみ拾い」文化が世界の子供に伝播 全80チーム参加のサッカー大会、「+1」の理念に込めた願い【インタビュー】
日本の「ごみ拾い」文化が世界の子供に伝播 全80チーム参加のサッカー大会、「+1」の理念に込めた願い【インタビュー】

ジュニア年代の国際大会「コパ・トレーロス2025」が3月27日に開幕
静岡県御殿場市で3月27日から5日間、ジュニア年代の国際大会「コパ・トレーロス2025」が開催される。今回で14回目を迎える大会を2010年に立ち上げたのが、株式会社ファンルーツ代表取締役社長でFCトレーロス代表の平野淳氏だ。かつて海外を渡り歩き、各国の指導者ライセンスを取得してきた異色の経歴の持ち主は、その後FC東京や横浜F・マリノスなどJリーグ下部組織での指導を経て、小学生年代の育成に注力するようになった。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
チーム運営やスクール事業にとどまらず、“街クラブ”が国際大会を主催する――。そんなチャレンジを続ける根底には、自身が海外で生活している時に見た光景があるという。理念に掲げている「Football+One」(フットボール+1)の精神にも迫った。(取材・文=轡田哲朗/全2回の2回目)
◇ ◇ ◇
コロナ禍の時期を除き毎年開催し、今回で14回目を迎える大会は当初10チームほどの規模でスタート。それが今回はU-11、U-12の2カテゴリーで、それぞれ40チームが参加するところまで拡大した。
過去の大会には、現在の日本代表で活躍している選手も数多く参加していたという。それでも平野氏は「それを宣伝材料にしないようにしていて、大会の魅力を感じてほしいんです。いろいろな人からはもっと広告的に使ったらと言われますが、国際大会としても価値を高めたいですし、純粋に子どもたちに良い環境を作ることに注力しています」と笑顔を見せた。
そのような大会を設立した動機について平野氏は、自身が多くの国で指導者ライセンスを取得する際に見てきたものが影響を与えたと話す。
「ドイツやオランダには街クラブが主催の国際大会がたくさんあります。それこそ、手弁当で1万円くらいのスポンサーをたくさん集めて、お金が集まったら隣の国のチームを呼ぶような由緒ある大会がたくさんありました。日本では、そういうクラブが主催の国際大会はなかったと思うのですが、日本でも同じようなことをやることで、街クラブのブランドや価値も上がるんじゃないかと思い立ち上げました。今も企業やJクラブが主催するものはありますが、街クラブの主催する国際大会はあまりないと思います。自分たちの利益による余剰金やスポンサーさん、個人の方の協賛も含め、いろいろな方の協力で成り立っています」

ピッチ内だけではない国際交流の価値
「コパ・トレーロス2025」の参加クラブ一覧には、関東圏内のJリーグ下部組織の名前がずらりと並ぶほか、Jリーガーを輩出しているような名門ジュニアチームの名前もある。また、スペインからアトレティコ・マドリードのU-11チーム、ポルトガルからはスポルティングのU-12チームが参加するほか、オーストラリア、韓国、中国、台湾、ネパール、タイとさまざまな国からチームがやってくる。
平野氏には「もちろん本気で戦って世界を感じてほしい」というサッカーへの思いもある。実際に「アトレティコは過去最強のU-11と聞いています。スポルティングも前回の決勝で川崎フロンターレを5-0で破ったのですが、ヨーロッパでもトップレベルのチームです」と、欧州から参加する名門はネームバリューだけではなく実力も兼ね備えていると話す。
一方で、「なかなか海外に行けない家庭も多いと思いますが、海外へ行かなくても交流できますし、大会中に各国の子どもたちが交流する時間もある。そういうのこそ、一番やりたいことだったんです」とも話した。そこにはサッカーを通じて、別の価値も見つけてほしいとの願いがある。
「スポーツのいいところは競技力の向上だけでなく、周りのところにもあると思います。サッカーを通じて、いろいろな経験を子どもたちにしてもらいたいし、一生懸命やる先に国際交流などいろいろなことができると思っています」
その思いを表現できる短い言葉がないかと探していたところ、鳥取県サッカー協会の事務局長をしていた髙田貴志氏からアイデアをもらい、「Football+One」という理念が誕生した。

海外の選手も「日本の文化を経験できるのはプラスになる」
大会では回を重ねるごとに、そうした取り組みが実を結んできている。「それこそ、ごみを拾うような文化もそうですよね」と話す平野氏は、「過去の大会でも弁当を食べた後のごみをそのまま捨てていたのを、日本のクラブの子供たちが片づけているのを見て感じるものがあったようです。日本の違う文化を経験できるのはプラスだと思いますし、将来的に親日家になってくれたら嬉しいですね」と笑う。
また、「今回のU-11カテゴリーのファンルーツ・グローバルというチームはU-12に出場する台湾のチームの1歳下の子たちとのミックスで出場するんです。大会数日前に来日した台湾の子と合同チームを組むのですが、今回はドイツ人が監督をやります。なんとかしてみんなで理解し合ってやっていこうという努力でチームが成り立ちますし、そういう経験も提供しています」と、まさにサッカーをベースに言葉が通じなくてもコミュニケーションを取り、協力していく体験も用意している。
サッカーは全世界に広がる国際的なスポーツであり、欧州を中心に海外でプレーする日本人選手も今や数えきれないほどになった。そうしたなかで、小学生年代からサッカーを通じて国際交流の場を得られる大会は、双方にとって貴重な機会になるはずだ。
(轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada)