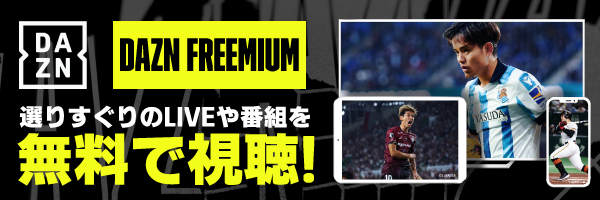- HOME
- 今日のピックアップ記事
- 開幕節ジャッジに「違い感じた」 選手、監督が変化実感…J目指す世界レベルの判定基準
開幕節ジャッジに「違い感じた」 選手、監督が変化実感…J目指す世界レベルの判定基準

判定基準が変わったJリーグ、審判はプレーの継続性を意識
今季のJリーグは、コンタクトプレーの見極めに関する判定基準について野々村芳和チェアマンが言及する中で開幕した。実際に選手や監督からは、その変化を実感する言葉が聞かれた。
【PR】ABEMA de DAZN、日本代表選手の注目試合を毎節2試合無料生中継!
2月10日に東京都内で行われたJリーグ開幕イベントの際、野々村チェアマンは今季のJリーグについて「ここを変えていこうという2つの観点」を提示。それを「1つ目はプレーの強度。2つ目はアクチュアルプレーイングタイム」と話した。
このプレー強度についてチェアマンは「世界のトップでプレーしてきた、体感してきた選手や森保監督にも、どういったところを変えなければいけないかを聞いてきた」として、「コンタクトプレー、強度というのは、強さ、深さ。世界のトップレベルでやってきた選手から何度も言われてきた部分」だと話した。
14日に金Jとして先行開催されたガンバ大阪とセレッソ大阪の試合では、コンタクトプレーとハンドの反則で与えられる直接フリーキックの数はG大阪が7本、C大阪が2本だった。C大阪の先制ゴール、G大阪が1-1にした同点ゴールがいずれも、木村博之レフェリーがファウルを認識しながらアドバンテージを採用してプレーを続けさせた好ジャッジから生まれたように、この数字は必ずしも反則の数と一致しない。しかし、開幕戦の熱気ある試合でオフサイドを除く反則の笛で止まった回数が9回だったという事実は、それだけプレーが継続されたことを示す。
実際に長年欧州でプレーした経験を持つC大阪のMF香川真司は、コンタクトプレーについて「結構流しているな、という印象はあった」と話した。
そして、15日にヴィッセル神戸との開幕戦を控えていた浦和レッズのマチェイ・スコルジャ監督は、この基準の変化について「金曜日の試合を見て違いを感じていた。(翌日の)試合前のロッカールームで選手たちにはその話もした」と話す。スコルジャ監督は23年に1シーズン、昨季は9月以降に浦和の指揮を執った。約1年半にわたって日本での監督経験を持つことから、近年のJ1がどの程度の基準で判定されていたかを知っている。
神戸と浦和の試合は、直接フリーキックの数を見ると神戸に15本、浦和に9本だった。前日の大阪ダービーと比較すれば2倍以上の数になったが、荒木友輔レフェリーが細かく笛を吹いて止めた印象はなかった。むしろ、反則で止めるもノーファウルで流すもどちらでも良さそうなものは、止めていない印象すら受けた。前日のゲームと比較するなら、判定基準に多少の変化を加えようが「ルールが変わるわけでない」(野々村チェアマン)という部分で、明確な反則の数が多かった印象だ。
スコルジャ監督も今季の判定基準について「開幕で違いを感じることができた。今後もそうなるのかは興味深く見ていきたい。レフェリーにとって簡単な状況ではないと思う。選手がたまに驚くような場面も神戸戦ではあった」と、判断の変化を求められる審判団へ気遣いも交えつつ実感を話した。
試合の中でインプレーの実質的な時間を指すアクチュアルプレーイングタイムについては、主にセットプレーにかける時間といったチームや選手サイドに依ってくるものと、交代の手際など審判側に依るものが混在する。これは少し長い目でデータを見ていく必要がありそうだが、少なくともピッチ上のコンタクトプレーに関しては変化が感じられた。
スコルジャ監督の言葉のどおり「今後もそうなるのか」という視点も必要になりそうだが、少なくとも開幕節では今後の方向性が示されたと言えそうだ。
(轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada)