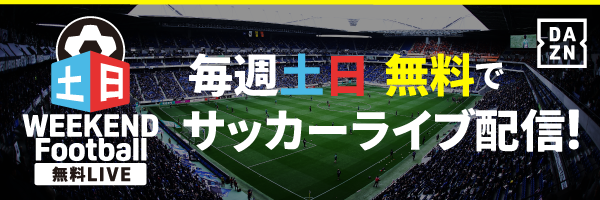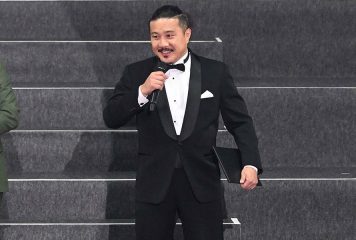佐野海舟の通訳で受けた衝撃…異次元の“当たり前”「日本の育成年代でもっと大事にしたほうがいい」【インタビュー】

マインツ女子で指揮を執る山下喬が提言「育成年代の指導者層を強化しないと…」
ドイツ・ブンデスリーガのマインツ女子で監督として指揮を執る日本人指導者の山下喬は、現在マインツ男子で活躍する佐野海舟の通訳としてもサポートしている。ほぼすべてのトレーニングに帯同しているなかで衝撃を受けたエピソードを明かし、「日本の育成年代でもっと大事にしたほうがいいところかもしれません」と持論を展開した。(取材・文=中野吉之伴/全4回の4回目)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
元日本代表FWの岡崎慎司とドイツで設立したFCバサラ・マインツというクラブで、チームを11部から6部まで引き上げた経歴を持つ山下喬は、現在ブンデスリーガクラブのマインツで女子トップチーム監督を務めている。
女子サッカーの置かれた状況について「以前と比べて間違いなくいろんなところで改善が進んでいる」ことは評価したうえで、「まだまだいろんなところに問題があるんです」と明かしてくれた。
今シーズンから女子U-17ブンデスリーガが廃止になった。「全国規模でやると行動範囲も広く、お金もかかる。それだけのことをやっても、U-17ブンデスリーガからトップチームへすぐに昇格できる選手はほとんどいない」というのが理由として挙げられている。プレー人数やチーム数も男子に比べて少ない女子サッカーでは、年代別のカテゴリーも多く持てず、育成最後のカテゴリーがU-17で、その上は大人のチームというのが現状だ。あまりに年齢的な幅が広すぎる。
「今、U-17女子チームは地域のU-15男子リーグに所属しています。ただそうした環境でサッカーをしてきた彼女たちが、大人の強豪チームでサッカーをしようとしても、基本的なことが身に付いていない。育成年代の指導者層をさらに強化しないと、この問題は解決されないと思います。女子チーム自体も少ないし、そこの認知度も高くない。資質はあるんだけど、技術的にも個人/グループ戦術的にも、基本的なことを学んでない子たちがすごく多い」
ドイツ女子サッカーは発展途上であり、様々なことが整理され始めた段階だ。日本サッカー界のほうが充実している部分も多くあるだろう。その一方、サッカーへの取り組み以外で興味深い違いもある。
以前、女子バスケットボールのブンデスリーガでプレーしていた安間志織(フライブルク)にこんな話を聞いたことがある。
「例えば日本だと、バスケットボールを一生懸命やっているチームでは基本そればかりになるけど、ドイツだとチームメイトに医大に行っている子がいたり、法学を学んでいる子がいたり、政治情勢についてディスカッションしたりする子がいて驚いた。こんな環境は私の周りにはなかったなぁって」

特定スポーツのみという感覚は「日本の育成スポーツのあり方における弊害」
あるスポーツを本気でやるなら、それを第一に精一杯やるという感覚が強い日本だと、それ以外のことに手を出すのは「二兎を追うものは一兎をも得ず」と一蹴される可能性があるし、とかく「強化」に目が向けられがちである。
スポーツとは本来、日常生活における大事なゆとりやリラックスのためにあるものだ。スポーツの語源を探るとラテン語の「deportare(デポルターレ)」に辿り着く。
「日常生活の中には労働など十分すぎるぐらい大変なことがあるのだから、自分たちが健全に幸せに暮らしていくためには、そこから離れて、好きなことに没頭できる時間と空間が必須なのだ」という解釈がされ、特に欧州ではこの考えがベースにある。例えばサッカーはドイツにおいて、「人生で最も大事なカテゴリーには入らないものの中で一番大事なもの」という言われ方をよくするのはそのためだ。
「確かにそのスポーツばかりになってしまうのは、日本の育成スポーツのあり方における弊害かもしれないですね。ドイツにサッカー留学に来る子たちを見ても、日常生活のあり方がよくなかったり、ドイツ語ややるべきことを学ぶ意欲がほとんどない子たちが少なくないです」
自主的な山下は、現在マインツで活躍する佐野海舟の通訳としてサポートもしている。ブンデスリーガで上位に食い込むチームの練習を目の当たりにしている彼が、とても印象的な話をしてくれた。
「ほぼすべてのトレーニングに帯同していますけど、みんなまったく手を抜かない。球際ではバチバチ行くし、攻守の切り替えもものすごく速くて、トレーニング強度が高い。彼らが取り組んでいる『当たり前』のレベルや意識がすべて高いんです。シンプルなパス練習をしても、細かいポジショニングや動作に、試合でのプレーをイメージしたものがある。どうやってマークを外すのか、どのタイミングで動き出すのか、どこを見ておいて、どこへ展開するのか。そうした練習と試合を結び付ける作業のレベルがとても高いと感じています。このあたりは男子でも女子でも、日本の育成年代でもっと大事にしたほうがいいところかもしれません」
結果主義ではなく成長主義の育成…「現場レベルに落とし込むのが難しい」
ルーティンワークで基本技術や身のこなしに取り組むのが悪いわけではない。ただドリル形式で、考えたりイメージすることなく何度も繰り返すことがサッカーにおける成長につながるわけではない。1つ1つがばらばらにならず、それぞれのプレーや動きが、いつ、どこで、なぜ、どのように使われるべきかなどを常に意識して、取り組める環境を作っていくことが大切と言えるだろう。
山下がマインツ女子での取り組みを話してくれた。
「ブンデスリーガでは、育成において『結果主義ではなく、もっともっと成長主義になるべきだ』って動いていますが、これを現場レベルに落とし込むのが難しい。僕ら指導者のレベルや経験にしても、まだそこまでではない。トップの強化部長を招いて、まず『マインツのサッカーとは? マインツDNAとは?』というベーシックな話をする女子指導者ミーティングを今度行います。そういうところからやっていこうと」
道が険しかろうと長かろうと、一歩を踏み出さなければいつまでもたどり着けない。
(中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano)

中野吉之伴
なかの・きちのすけ/1977年生まれ。ドイツ・フライブルク在住のサッカー育成指導者。グラスルーツの育成エキスパートになるべく渡独し、ドイツサッカー協会公認A級ライセンス(UEFA-Aレベル)取得。SCフライブルクU-15で研修を積み、地域に密着したドイツのさまざまなクラブで20年以上の育成・指導者キャリアを持つ。育成・指導者関連の記事を多数執筆するほか、ブンデスリーガをはじめ周辺諸国で精力的に取材。著書に『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』(ナツメ社)、『世界王者ドイツ年代別トレーニングの教科書』(カンゼン)。