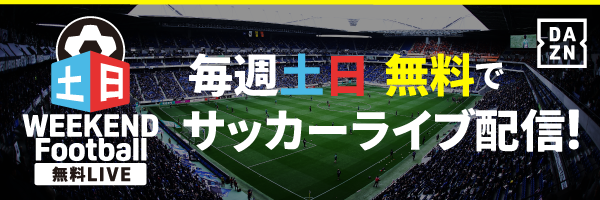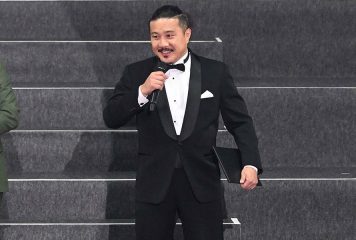選手兼指導者の25歳日本人が欧州で実感 威圧的言動の問題点…「褒める」が正解ではない指導法【インタビュー】

オランダで選手兼指導者として過ごす桝田花蓮、選手と指導者の関係性に持論
早稲田大学ア式蹴球部女子部から在学中にコスタリカへ飛んで活躍し、その後は将来的に指導者になりたいと渡欧を決意した桝田花蓮。現在オランダのデンハーグで仕事をしながら、選手兼指導者として奮闘しているなか、選手と指導者の関係性やコミュニケーションについて「ハッとしました。自分の価値観や見方も常にアップデートしないとなって感じましたね」と、自身の体験を基に思いを語ってくれた。(取材・文=中野吉之伴/全3回の3回目)
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
◇ ◇ ◇
オランダのデンハーグで仕事をしながら、サッカー選手として、そしてサッカー指導者として奮闘している桝田。ウェールズサッカー協会でC級ライセンスを獲得した彼女が、オランダでサッカーをしているなかで、選手と指導者との関係性やコミュニケーションについて強く感じたことがあるという。
「今、私はオランダの3部にあたるリーグに所属するクラブでプレーしているんですけど、監督が結構、ガツガツ系なんですよね。だから練習中にもガーって大きな声でこっちにいろんなことを言ってくるんです。『オランダでもこういうタイプの指導者はいるんだな』って私は思っていたんですけど、違うのは選手の態度かなって。
納得できないことを言われたらみんな黙っていられないから、しょっちゅう選手と監督が言い合っています。でも面白いのはガーって監督が言ってきたのに、そうやって選手が話し出したり、話したいという姿勢を示したら、ちゃんと話は聞くんですよ。大きい声で指示を出すのが良いか悪いかは置いといて、選手とコーチの立場が上下になっていないのはすごい感じます」
さまざまなハラスメントの事例やそれに応じた規約によって、日本における指導者から選手へのアプローチも一昔前と比べれば少なからず変化はある。だが、現在でもコーチや監督は選手よりも上の立場という意識がどこか漂っているのは否めないのではないだろうか。
欧州のようにそれぞれが自分の意見を口にするのが当たり前の社会では、相手に主張されることが前提としてあるなかで、自分の本気度を伝えるためにエネルギー全開で大きな声を出すという手段を取ろうとする指導者もいる。
「あとオフ・ザ・ピッチというか、練習や試合の前後は本当にいい人。すごい気さくに話せる。監督はあまり英語は喋れないんですけど、それでもいつもコミュニケーションを取ろうとしてくれるんです。ほかの選手ともよく喋ってます。だからみんなも監督のことを嫌いとかはまったくない」

「『こういうコーチもいるよな』で済ましてちゃダメ」と語る訳
ただ、「オン・オフの切り替えがあるから」といって、そうしたアプローチが常に効果的かというと、いらぬ誤解や不穏な空気をもたらす危険性もある。その点について、桝田はチームメイトの反応から気付いたという。
「私はたぶん日本でのこともあって、怒鳴られてもそんなに気にならない。変に慣れてしまっているのか、嫌だなとはそんなに思わないんですよ。ただこの前、前のチームメイトが試合を見に来てくれたんですけど、監督のそうした態度にびっくりしていたんです。その子はノルウェー人なんですけど、あとで話をしていたら、すごい嫌だったと話をしてくれて。『自分も嫌だし、チームでそんなことをされているカレンを見てるのも嫌だった』って。その子からしたら『なんで怒鳴る必要があるの?』『怒鳴る必要なんてない。普通に話してくれればいいのにって』ということなんです。その拒否反応を見て、『ああ、自分って慣れちゃってたんだな』って改めて感じましたね」
以前、オランダのユトレヒトで地元小学校の体育教師として働いていた安井隆氏から「欧州において、特にオランダにおいては、『大人であるというのは自分の負の感情をコントロールできる人』というふうに言われています。暴力は論外。論理的な説明もなく、ただ怒鳴るのはあり得ないと同僚とよく話をしています。そうではないアプローチで子供たちと向き合うのが大人であるし、教育者の役割」という話をしてくれたことを思い出す。
「その子のチームでは今季から新しく男性の監督が入ったんですけど、上から命令口調で言うわけではないけど、すごいパワフルに入ってくるタイプで。チームの女の子たちみんなが、そうやって男の人に上から強く言われるのが本当に嫌だったようで、その人は最近辞めることになったと聞きました。こっちでこれから指導者としてやっていくうえで、こういう感覚は知っておかないといけないとすごい思いましたね。
私は別に怒鳴ったりとかしないですし、ヨーロッパで育ったみんながみんな拒否反応を示すわけではないのかもしれません。でも彼・彼女たちからしたら、怒鳴られること、威圧的に言われることは、それだけ『嫌!』って受け止められるほどのことなんだという感覚は持っておかないといけない。『こういうコーチもいるよな』で済ましてちゃダメで、ちゃんと気をつけなきゃいけないなって。将来的に私が同僚とか、子供たちの両親にそういうタイプの人がいた時、選手がどう思うかを理解できないと対応することもできないなって、ハッとしました。自分の価値観や見方も常にアップデートしないとなって感じましたね」

「『嫌だ』『悲しい』『嬉しい』という感情もちゃんと伝えたらいい」という学び
一方、立場が逆転するのもまたおかしい。昨今の日本では、子育てにおいて褒めることだけが正解という風潮さえもあったりするが、それでは子供たちが「何がミスか」を学ぶ貴重な機会を奪ってしまう。当たり障りのないアプローチばかりでは、子供たちがフワフワしたところから戻ってこれないではないか。
「怒るのと自分の感情をちゃんと出すっていうことの境界線が難しいなと思っています。アフタースクールの子供たちに教える時は、話しを全然聞いてくれないこともあるんです。1回、自分の感情そのままに伝えたこともあります。『聞いてもらえなくて悲しいよ』とか、『せっかくみんなでこうやって集まってサッカーしてるのに、練習を邪魔されたらすごい嫌なんだ。私はこの練習でみんなに楽しんでほしい』って感情とともに伝えたら、すごいちゃんと聞いてくれたんです。今までにないぐらいちゃんと聞いてくれた。あとで私のところに来て、『ごめんね』って言ってくれた。
それまでは大人と子供の関係性で接してるみたいな意識があったんですけど、人と人として接したという感覚がありました。感情を抑えて大人ぶることだけが大事じゃなくて、『嫌だ』『悲しい』『嬉しい』という感情もちゃんと伝えたらいいんだなって。大人ぶる必要はないっていうか、そこをすごい感じました」
日本とは異なる習慣、感覚、常識のなかで、母国語ではない言葉でコミュニケーションを取るのだから、様々な面で驚きもあるだろうし、上手くいかない時もある。そうしたやり取りのなか、どれだけ自分が先入観にとらわれていたかに気づける時が来る。
大人と子供の関係性でどちらかが上になる必要はないのだ。どの国であろうと、誰とであろうと、互いを尊重し、互いの意見に耳を傾け、そのなかでコミュニケーションを図り、より良いものを探し求めていくほうが互いに得られるものは大きいはずではないか。
(中野吉之伴 / Kichinosuke Nakano)

中野吉之伴
なかの・きちのすけ/1977年生まれ。ドイツ・フライブルク在住のサッカー育成指導者。グラスルーツの育成エキスパートになるべく渡独し、ドイツサッカー協会公認A級ライセンス(UEFA-Aレベル)取得。SCフライブルクU-15で研修を積み、地域に密着したドイツのさまざまなクラブで20年以上の育成・指導者キャリアを持つ。育成・指導者関連の記事を多数執筆するほか、ブンデスリーガをはじめ周辺諸国で精力的に取材。著書に『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』(ナツメ社)、『世界王者ドイツ年代別トレーニングの教科書』(カンゼン)。