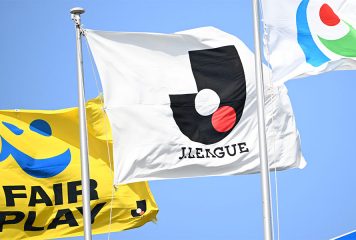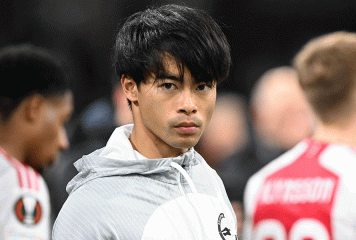現役引退のレジェンド「もっと覚悟を持って」 後輩へ受け継ぐ“プライド”「ねじ伏せてやる」

現役引退の宇賀神が浦和への思いを語った
浦和レッズのDF宇賀神友弥は12月8日のリーグ最終節アルビレックス新潟に途中出場でプレーし、現役ラストゲームを終えた。「たくさんブーイングもされたし、たくさん文句も言われたけど、応援してもらった」と、最後に場内を1周した埼玉スタジアムへの思い入れと後輩たちに受け継いでほしいプライドについて語った。
【PR】ABEMA de DAZN、日本代表選手の注目試合を毎節2試合無料生中継!
宇賀神は中学年代のジュニアユースから6年浦和の下部組織でプレーし、トップ昇格を果たせず流通経済大へ進学した。そこでは同じさいたま市に本拠を置く「大宮アルディージャに入団して、浦和を倒す」と意気込んでいたのは知られた話だ。しかし、2009年に浦和のトップチームに練習参加すると当時のフォルカー・フィンケ監督に絶賛され特別指定選手登録、翌シーズンに正式加入と、クラブ史上初のアカデミー出身の大学経由トップチーム入りのキャリアになった。
サイドバックやウイングバックを主戦場に、対人プレーはガツガツと行きながらも全体的にはチームのバランスを見ながらプレーするスタイルだった。反骨心の強さを持ち味にキャリアを歩んできただけに、デキの悪い試合をしてサポーターから批判を受けた次の試合ほど好プレーを見せた。「まずいプレーをした次の試合は大切」と話すことも多かったが、2試合続けて悪いゲームをしないこともまた多くの監督から信頼を受けた理由の1つにもなるのだろう。そのような試合では、ファーストプレーで「ガツン」といくのが定番だった。
リーグの中で資金力のあるクラブだけに、補強で有力選手を獲得することが多かった。その中で鈴木啓太、長谷部誠、田中達也らの高卒生え抜き選手の活躍はあったが、なかなか下部組織出身者のレギュラー定着は難しかった。それでも、フィンケ監督時代に山田直輝や原口元気らの世代を中心にトップチームに定着する選手も増えた。その中では大卒のため少し年上の宇賀神だが、アカデミー出身者では最も長い間レギュラーとしてプレーしてきた選手だろう。
浦和サポの「ブーイングも文句も力になっていた」
その宇賀神は、最後の取材対応となった試合後に埼玉スタジアムでの戦いについて問われ「埼玉スタジアムでは勝利以外いらない。ピッチに立ったからにはチームを勝たせないといけない、それだけを思っていた」と、ラストゲームで後半35分に途中出場してキャプテンマークを巻いてプレーした時間について話した。
浦和在籍中、埼玉スタジアムでタイトルを決めた試合は3回あった。「僕はケガで交代してしまったけど、浦和で初タイトル。人生で初めてうれし泣きができた」と話した16年のルヴァン杯決勝、AFCチャンピオンズリーグを制した17年、そして宇賀神のスーパーボレーが決勝点になった18年の天皇杯決勝と、歓喜の思い出がある。特に17年のACLは、決勝トーナメントで全てアウェーの初戦を引き分け以下で終え、ホームの第2戦で勝利して栄冠に輝いた。
サイドを上下動しながら、数メートル先の観客席から多くの声を受けてきた宇賀神は「あの声援は力でしかないし、どんなブーイングも文句も力になっていた。逆に力に変えないといけないと思っていた」と、その思い入れを語る。
「まず大前提として、僕はJ1では浦和でしかプレーしなかったけど、埼スタで対戦する時は相手の方がすごく燃えていて、こいつらを黙らせてやるという思いに勝たないといけないプレッシャーもある。だけど、僕はそのプレッシャーを楽しみにしていたし、そういう感情のチームや選手もねじ伏せてやると思っていたのを思い出した。熱い思いや責任、覚悟を全員が持たないといけない。埼スタのピッチで戦うのはどういう意味があるのか、もっと覚悟を持って戦わないといけない」
現役引退のタイミングが、盟友であり浦和でクラブ最多ゴールを更新したエースFW興梠慎三と同じタイミングだっただけに、最後の場内1周の時を思い返して「試合前からうすうす気づいていたけど、興梠慎三と一緒のタイミングで引退しちゃいけないなと。やっぱり偉大だと思った」と苦笑いした。それでも、「意外に3番や35番がいっぱいいて、たくさんの人に応援してもらっていたなと。たくさんブーイングもされたし、たくさん文句も言われたけど、応援してもらった」と、自身の背番号を掲げるサポーターの姿を脳裏に浮かべて笑顔を見せていた。
セカンドキャリアでは、「浦和レッズのゼネラルマネジャー(GM)になるのが夢」と明言し、来季もクラブに残るという。「常勝軍団にするのはもちろん、浦和レッズと言ったらというものを作りたい。恐らく今の印象は、サポーターがすごい、いい選手がいるよねで終わってしまうと思う。浦和のサッカー、浦和の選手とは何かを作りたい。それがあってこそ常勝軍団になれる。それを自分が作っていきたい」と、すでに次の活動へ向け思いを馳せていた。