「あの試合は理想」 中田ら“黄金のカルテット”不在で生まれた韓国との充実の一戦【コラム】
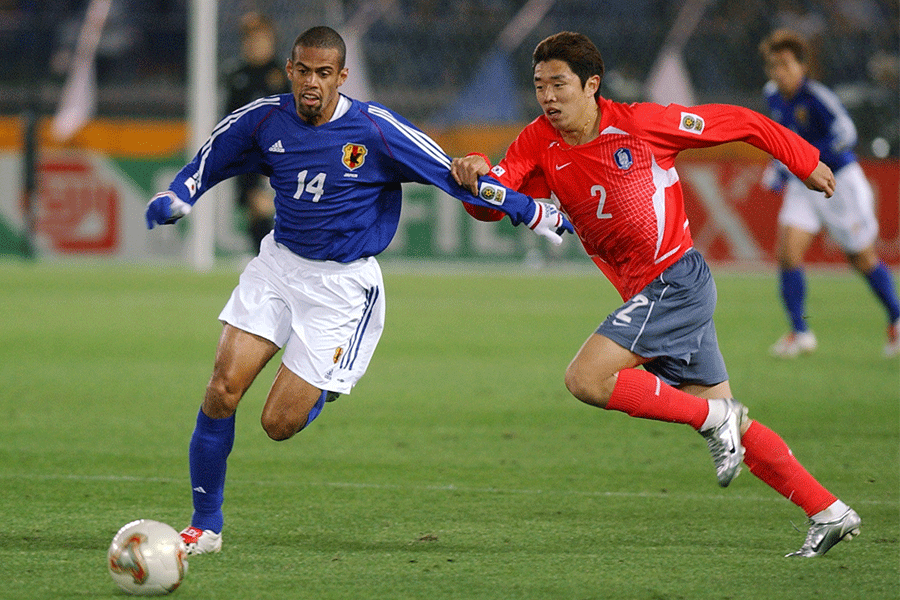
【カメラマンの目】2003年12月10日の日韓戦は「サッカーとしての理想」
国の威信を賭けて戦う代表戦の舞台で、“サムライブルー”の愛称を持つ日本代表は人々の心を熱く揺さぶる数々のドラマを作り上げてきた。カタール・ワールドカップ(W杯)では、世界屈指の強豪であるドイツ代表とスペイン代表を撃破する殊勲の勝利を挙げた。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
さらなる高みを目指して世界の舞台で挑戦を続けている日本だが、当然アジアとの戦いでもいくつもの好勝負を演じてきた。とりわけ互いに強いライバル心を持つ、韓国との一戦は激しい攻防が繰り広げられ、記憶に残る試合となることが多い。
韓国戦で友人のカメラマンと話をすると、「あの試合は良かった」と意見が一致するものがある。ピッチに描かれたスペクタクルはわずか45分間のことだったが、20年以上の歳月が過ぎたいまでも心に強く焼き付いている。
サッカーゲームにおける勝敗は勝利、敗北、引き分けの3つ。しかし、内容となると、それこそ試合の数だけ存在することになる。勝利という結果を出しても内容的に不満が残る試合もあれば、たとえ一敗地にまみれても好印象として記憶に刻まれるゲームもある。
そして、最終的な結果はどうであれ、選手たちが願う勝利への欲求が極限に達した時は至極、単純なものになるということだ。戦術云々の技術は勝敗の帰趨を決する要因ではなくなる。時間稼ぎや、つまらないファウルによる相手の長所を封じるプレーはピッチから消え去り、レベルの低い駆け引きや打算は入り込む余地がなくなるのだ。
持てる能力を100%、いやそれ以上に出しサッカー選手としての本能のままに勝利を目指す。そうした試合は必然的にシンプルになり、見る者を魅了する内容へと誘う。このサッカーとしての理想となる試合を、日本がライバルに対して見せたのが2003年12月10日に行われた試合だ。

今アジアカップの決勝戦で日韓戦は実現するのか
この時、日本は12月4日からホストカントリーとして、第1回東アジアサッカー選手権(現E-1選手権)を戦っていた。参加国は韓国、中国、香港の4か国。総当たりのリーグ戦で行われた大会で、日本は韓国との最終戦を前に隣国のライバルとともに2勝を挙げ、しかも得失点差でも並んでいた。だが、総得点で韓国が上回る状況で、日本に残された優勝の手段はアジアの虎から勝利をもぎ取ることしかなかった。
チームはヨーロッパがシーズン中だったため、指揮官ジーコが主力として位置づけていた海外組が不在の編成で大会に臨んだ。ライバルとの一戦の先発メンバーはGK楢﨑正剛、DF山田暢久、宮本恒靖、三都主アレサンドロ、中澤佑二、坪井慶介、MF福西崇史、小笠原満男、遠藤保仁、FW久保竜彦、大久保嘉人。多少コンディションが悪くても中田英寿ら海外組の起用を最優先にしてきたジーコのチームで、彼らが不在となった試合で好ゲームが生まれることになるのだった。
試合はわずか前半18分で2枚のイエローカードを受けて大久保が退場し、日本は早々に数的不利となる。しかし、この逆境が日本の選手のハートに火をつけ、ブラジル人指揮官を大胆にさせた。ジーコ監督が現役時代に感じていた、負けることが絶対に許されない隣国アルゼンチンへの強烈な対抗心を、指揮官の立場となったこの試合で蘇らせたように韓国撃破に向けて強気の采配を揮う。
後半開始からディフェンダーの中澤から本山雅志に、ボランチの福西を藤田俊哉に交代。ボールの持てるテクニシャンの攻撃的ミッドフィルダーを2人投入し、状況打開を目指す。左サイドの三都主も果敢にオーバーラップを仕掛け攻撃を活性化させた。指揮官の勝利への思いは選手たちに伝播され、日本は攻撃の勢いを加速させ韓国を追い込んでいった。
日本の全選手が相手ゴールの攻略を強く意識し、韓国の牙城を小細工なしに、ひたらす力尽くによって一気に攻め落とそうとする、その姿には心が熱くなった。数的不利をものともせず、韓国守備陣に攻撃を跳ね返されても果敢に挑み続けた日本。しかし、スコアを動かすことはできず、試合は0-0の引き分けに終わり自国開催での優勝を逃すことになる。
勝利という結果は出すことができなかった。優勝カップも韓国の手に渡った。だが、だからと言ってこの試合の日本を酷評する必要は全くない。内容となれば日本は後半に限定されるが、数的不利のなか韓国を自陣に釘付けにする圧倒的なアタッキングサッカーを展開し、強いインパクトを残したのだから。
現在、中東カタールの地でアジア王者の称号を目指して戦っている日本は、決勝トーナメントに進出したものの、グループリーグでは低調な試合内容に終わった。決勝トーナメントでは奮起し、語り継がれるような名勝負を作り上げることができるか。できることなら決勝の舞台でライバル韓国と相まみえ、両チームが力を出し合う名勝負となれば最高のエンディングになるのだが……。
(徳原隆元 / Takamoto Tokuhara)
徳原隆元
とくはら・たかもと/1970年東京生まれ。22歳の時からブラジルサッカーを取材。現在も日本国内、海外で“サッカーのある場面”を撮影している。好きな選手はミッシェル・プラティニとパウロ・ロベルト・ファルカン。1980年代の単純にサッカーの上手い選手が当たり前のようにピッチで輝けた時代のサッカーが今も好き。日本スポーツプレス協会、国際スポーツプレス協会会員。



















