中田英寿が「精彩を欠いた」中東アウェー戦 イランでの“異変”は現役引退の伏線だったのか【コラム】

日本代表を牽引した中田英寿の雄姿を回想
中田英寿というサッカー選手の勝負に対する集中力の高さを知った瞬間がある。それは25年以上も前の試合で、わずか数秒の些細な出来事だった。同じ場面は以前にも目にしたことがあり、その後にもカメラのファインダーを通して何度も見たが、この時は日本サッカーの命運を賭けた重要な一戦だったということもあり、そのありふれた光景を鮮明に覚えている。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
その出来事は1997年9月28日、ワールドカップ(W杯)本大会への初出場を目指す日本代表が、アジア最終予選で宿敵・韓国代表と対決した一戦でのことだった。
試合の流れは日本のホームゲームだったとはいえ、韓国が得意としているフィジカルと熱きハートを前面に出した激しいプレーに晒されて、失点への恐怖を感じながらの展開が続いた。当然、攻撃の起点となる中田にも厳しいマークがついていた。そうした状況で突破口を開こうとする中田に目が留まった。
ボールがタッチラインを割り、試合の流れが止まる。ここで韓国のマークの集中力も一瞬途切れた。このチャンスを中田は見逃さなかった。そのジェスチャーからはスローインでボールを入れる味方選手に、すぐに自分にボールを渡してくれと要求したように読み取れた。
しかし、この動きに気づいた韓国の選手が素早く中田のマークに付く。サイドラインでボールを持った味方の選手は、わずかだが反応が遅れ中田の思いを汲み取れない。中田はマーカーの集中力が途切れ、フリーの状態でボールが受けられるチャンスをものにできず残念な表情を見せた。
このプレーで中田にボールが渡っていたとしても、その流れからゴールが生まれたとは限らない。試合は後半22分に日本が待望のゴールをアジアの虎から奪取するが、終盤の連続失点で1-2の手痛い逆転負けを喫することになる。韓国の激しい厳しいマークを受けるなかで、ほんの一瞬の相手の気の緩みに乗じて攻撃を仕掛けようとした中田の集中力の高さを今でも鮮明に覚えている。
ライバルとの一戦に敗れた日本には、続くカザフスタン戦の成績不振によって監督解任の衝撃が走る。こうしたフランス本大会までの厳しい道のりに立ち向かうチームを、才能にあふれた若きミッドフィルダーは牽引し、見事に踏破してW杯初出場を果たす。続く自国開催のW杯のピッチにも立ち、精神面でそれまでの日本人選手にはあまりいなかったタフさを兼ね備えていた中田は、2006年ドイツ大会を目指すチームではキャプテンに任命された。いよいよ円熟味を増していく。そう思われた。
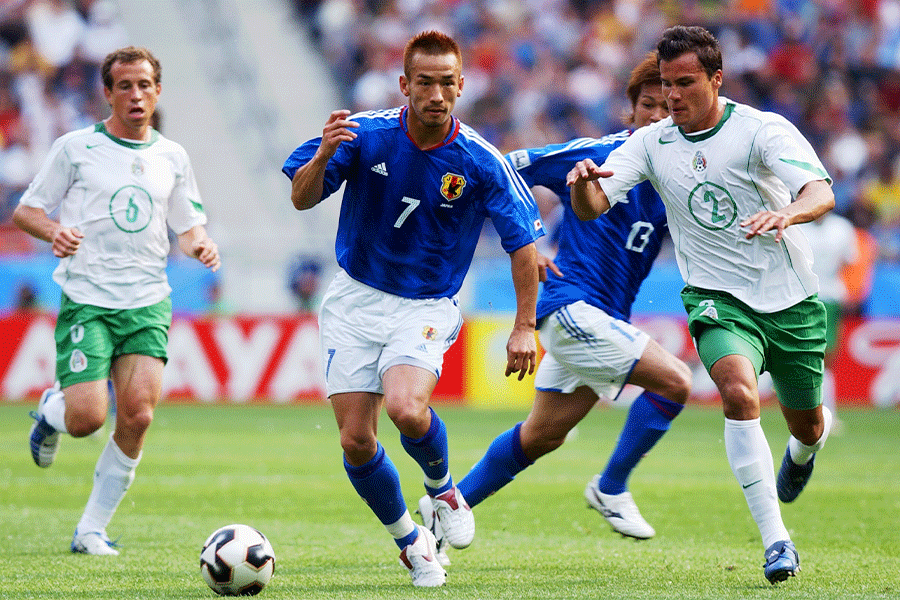
超満員に膨れ上がったアザディ・スタジアムでの中田のプレーに違和感
抜群のボディーバランスで相手のマークを跳ね返し、高精度のパスでゴールを演出。チャンスと見れば自らも積極的に得点を狙いにいく。美しいフォームから放たれるシュートは相手ゴールを強襲した。
だが、中田が代表で地位を確立するまでの過程は、順風満帆だったわけではない。技術、精神面とサッカー選手に必要なすべての要素を持った中田だが、その特筆すべき部分は相手の急所を突くキラーパスである。世界基準で戦う中田は、目指すレベルも高く、その思いをプレーで表現した。
中田が繰り出すパスは相手に対応させないことを考え、通常を凌ぐスピードがあった。彼の頭のなかで創造される攻撃を成功させるためには、受け手がゲームの流れを瞬時に読み、意表を突いたパスに対応するための高度なトラップ技術と、適切なポジショニングが求められた。
そうした勝利のために妥協を許さない中田のアプローチは、時に味方の選手もイメージを共有することができず、ミスパスとなることもあった。当時は対応できないほうが世界で必要なレベルに達していないからだという受け手を批判する意見があったが、結果的につながらないパスを高く評価する姿勢は、必ずしも正しい見解とは言えない。
しかし、中田自身の歩み寄りと、周囲の選手が次第に彼の意思を理解することによって、そうした世界基準を意識するあまり、連係を欠くようなプレーは徐々に減っていくことになる。
そうしてチームの中心としての地位を確立した中田だったが、彼の異変を感じたのが2005年3月25日、W杯ドイツ大会のアジア最終予選での対イラン戦の試合だった。10万人収容のアザディ・スタジアムは超満員に膨れ上がり、騒然とした雰囲気のなかで行われたアウェー戦で、日本は1-2で敗れることになる。
この敗戦はグループ4チーム中3位に転落した日本の成績以上に、いつもの中田ではなかったことが気になった。試合後、ホテルに戻り「一体、中田はどうしてしまったんだろう」と知り合いのライターに言ったことを記憶している。

小野伸二、中村俊輔のほうが上回る部分がありつつも…最も光彩を放つ
ジーコを指揮官とした当時の日本には、スター選手が中盤に揃っていた。そのなかでもかつてのブラジルの英雄からキャプテンを任命された背番号7は特別な存在だった。ボールテクニックだけで比較するなら、小野伸二のほうが上だったかもしれない。ゲームメイクという部分に特化したら、中村俊輔のほうがチームを自在に操っていた。守備力で言えばボランチの福西崇史や稲本潤一のほうが勝っていた。
しかし、強靭なフィジカルは敵を寄せつけないだけでなく、ディフェンスに回ればボールハンターとなって相手を追い込み、攻撃ではチームを勝利へと導く決定的なプレーを見せた。その高い技術と強い精神面をパワーの源とした、攻守に渡ってチームに貢献するプレーは、タレントの揃った中盤の選手のなかにあって、最も光彩を放っていた。
その中田がイランとの試合では厳しいアウェー戦だったことを考慮しても、プレーに精彩を欠いた。なにより身体にしなやかさがなく、サッカーの基本であるトラップが決まらなかった。
もしかして、それは始まっていたのかもしない。
中田は06年6月22日のW杯ドイツ大会の対ブラジル戦をもってスパイクを脱ぐことになる。代表引退ではなく、選手としての終止符を打ったことには驚かされた。
だが、対イラン戦で感じた中田の異変は、彼自身が最も分かっていて、そのころから理想とするプレーを表現できないことに、気がついていたのかもしれない。高い技術と精神面を併せ持っていた中田は、世界の舞台で臆することなく戦い、日本サッカーに革新をもたらした。彼が代表の舞台で目指した高き頂へと挑戦する姿勢は、その後に続く世界で戦う日本人選手たちの指針となっていることは間違いない。
徳原隆元
とくはら・たかもと/1970年東京生まれ。22歳の時からブラジルサッカーを取材。現在も日本国内、海外で“サッカーのある場面”を撮影している。好きな選手はミッシェル・プラティニとパウロ・ロベルト・ファルカン。1980年代の単純にサッカーの上手い選手が当たり前のようにピッチで輝けた時代のサッカーが今も好き。日本スポーツプレス協会、国際スポーツプレス協会会員。






















