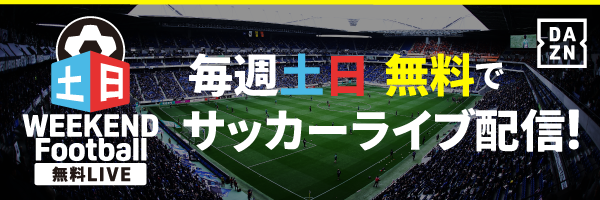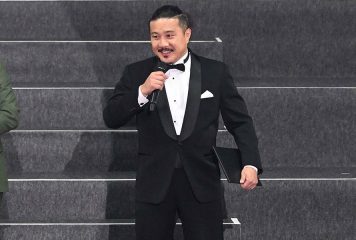日本代表に流れる「パスサッカーのDNA」 ミャンマー戦に見た伝統と“感覚”に頼る傾向

日本にサッカーの技術を伝えたビルマの留学生チョー・ディン
「こないして、『ふーとぼーる』をやったもんだがね」
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
岐阜の女学校に通っていたという祖母は、モンペ(スカート?)を両手でたくし上げるような仕草をした。その格好のままボールを蹴るのが「ふーとぼーる」だったと言っていた。小学生だった私が、「お婆ちゃん、それサッカーじゃないの?」と聞いても、「サッカー? ふーとぼーる言うてたよ」と答えるのみで、その時はなんだか腑に落ちないものがあったのだが、後にサッカーと呼ぶのは日本とアメリカぐらいで、世界的にはフットボールなのだと知った。
明治生まれの祖母が女子高生だった時代の岐阜といえば、けっこうな田舎だったと思う。そんなところにまで、フットボールはあったわけだ。女子がプレーしていたのも驚きだが、祖母の認識だとゴールへボールを入れるとか、パスをつなぐではなく、とにかく目の前に来たボールをポーンと遠くへ蹴飛ばすという、蹴鞠みたいなものだったようだが。
「日本サッカーの父」といえばデットマール・クラマーが有名だが、明治から大正にかけて広くサッカーの技術を教えた伝道師といえば、チョー・ディンの名が挙がる。ビルマ、つまり現在のミャンマーから来た留学生だった。当時のビルマは英国領で、チョー・ディンのサッカー観はスコットランド由来だったという。
イングランド式とスコットランド式。サッカーには2つの流派があった。ロングボールを蹴って追いかけ、ドリブルで突撃していく勇猛なイングランド式に対して、スコットランド式はショートパスをつないでいく技術のサッカーだ。イングランドのジェントルマンたちは「男らしさ」を重視しており、パスですら「男らしくない」と批判していた。もし彼らが今日のポゼッションだのポジショナル・プレーなどを目にしたら、「軟弱極まりない堕落したフットボールだ」と憤慨するに違いない。
ただ、英国人が世界各国へ広めていったスタイルはスコットランド式が優勢だった。チョー・ディンが理路整然とした指導で技術を教えた日本も、スコットランド式の流れを汲んでいる。
ロシア・ワールドカップ(W杯)直前に解任されたバヒド・ハリルホジッチ監督は、「縦に速い攻撃」を志向していた。解任理由はいろいろあったと思うが、これも一つの遠因ではないかと想像している。

西部謙司
にしべ・けんじ/1962年生まれ、東京都出身。サッカー専門誌の編集記者を経て、2002年からフリーランスとして活動。1995年から98年までパリに在住し、欧州サッカーを中心に取材した。戦術分析に定評があり、『サッカー日本代表戦術アナライズ』(カンゼン)、『戦術リストランテ』(ソル・メディア)など著書多数。またJリーグでは長年ジェフユナイテッド千葉を追っており、ウェブマガジン『犬の生活SUPER』(https://www.targma.jp/nishibemag/)を配信している。