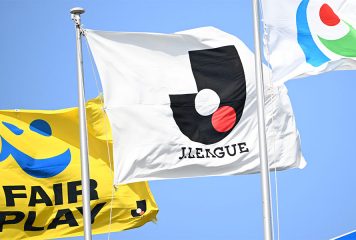恩師・城福浩が語る柿谷曜一朗の原風景(1) 「こいつ普通じゃないな」
“イマドキ”との戦いで出会った才気たち
長年、育成年代で指導を続けた城福が行き着いた答えは、十代の選手との向き合い方にテキストなど存在しないということだった。コミュニケーションが難しい年頃でもある。素直な気持ちを吐き出すことができる選手は稀だ。「イマドキ」の子どもに「イマドキ」の親。育成の場においては、その「イマドキ」との戦いでもある。
城福は1999年から約8年に渡ってナショナルトレセンコーチ、ユース年代の代表監督を歴任し、06年にU—16日本代表を率いてアジア選手権を制覇。翌年、若き日本代表と共にU—17ワールドカップ(W杯)の舞台を戦った。その現場で長年、戦い続けた男の答えは、「できることなんて限られている」だった。
「笑いさえしない選手だっている。俺たちは無表情な選手にもっと楽しんでいい、もっと言葉にしていいと言うことぐらいしかできない。ましてや、挫折を乗り越えさせることなんてできないよ」
そう振り返る城福は、自らが率いた代表に、チーム発足から2年半で延べ200人を超える選手を招集した。それは通例からすれば、倍の人数にあたる。「出張が多いぞ」と協会幹部から咎められても信念を曲げなかった。そこには意図があった。
当時は、トレセン制度の普及とともに協会主導の指導指針が津々浦々に広まり、全国にはステレオタイプの指導者が増えていった。そうなると、当然、制度の網に掛かる選手たちは似通ったタイプばかりとなる。だからこそ、まだ見ぬ才能を求めて全国を飛び回った。面白い選手がいると耳にすれば、街単位のサッカー大会だろうと、地方の中・高体連の地区予選だろうと足繁く通った。自分たちが作成した指針によって生まれた弊害、自責の念に突き動かされていた。
「ステレオタイプを壊さないといけなかった。協会が提唱するメソッドを広めることに関わったからこそ、そのメリットと反作用も感じた」
既成概念を疑うこと。それが原石を見出す第一歩だった。招集された200人の中には当時無名の東慶悟(現FC東京)もいた。環境が人を変えることは往々にしてあることだ。東は城福が率いる代表には数える程度しか呼ばれなかったが、それを一つのきっかけに大分ユースへと引き抜かれ、人生を変えた一人だ。