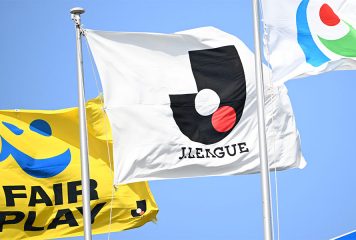城彰二の日本代表「W杯総括」 西野監督の続投支持「協会は曖昧なままにすべきでない」

【98年W杯日本代表・城彰二の視点】出場6大会で最も価値のあった4試合「守るだけのチームではなかった」
1998年フランス・ワールドカップ(W杯)から20年、6大会連続で世界最高の舞台に立ってきた日本代表にとって、今回のロシア大会で戦った4試合ほど、有意義な経験ができた大会はなかったと感じている。日本が長年築き上げてきたサッカーの何が通用して、何が通用しないのか――。
【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!
グループリーグで南米(コロンビア)、アフリカ(セネガル)、欧州(ポーランド)というタイプの異なる3カ国と対戦しながら2大会ぶりのベスト16進出を勝ち取ったことは、選手に大きな自信を与えた。今大会の日本が見せたサッカーで特筆すべきは、組織的な守備で相手の長所を消すことはもちろん、「ただ守るだけ」のチームではなかったこと。チャンスと見ればチーム全体で連動しながら攻撃を仕掛け、ゴールを奪いにいく意識がすごく高かった。
そうした日本の特長は、FIFAランク3位の強豪ベルギーと対戦したベスト16の一戦でもはっきりと表れていた。前半を0-0で耐えしのぎ、後半7分までに2ゴール。カウンターから柴崎岳のスルーパスに抜けた原口元気の1点目、相手を押し込みながら乾貴士がミドルシュートで決めた2点目とも、日本らしいスピードや技術が光った美しいゴールだった。
思い描いていたプラン以上の完璧なゲーム展開――2-0とリードした時間帯までの日本は、まさに非の打ちどころがなかった。勝負の行方は、間違いなく自分たちの手の中にあったはず。だからこそ、そこからの3連続失点は日本の自滅であり、「世界との差」が全て出てしまったように感じる。
個々の技術やフィジカル的な差、精神力、そしてゲームを読む力。ミスをしてはいけない局面でミスをしてしまう、悪い流れの時に断ち切れないなど、試合中の状況判断には強豪国との差を感じさせた。後半アディショナルタイムに喫した3失点目などは、まさにそれが一気に出た場面で、コーナーキックの場面で3点目を取りにいくのかが、チームとして少し曖昧だった。なんとなく数選手が相手ゴール前に上がり、なんとなく数選手を後方に残していたが、そこに甘さがあった。
ベルギーのGKティボー・クルトワがキャッチした瞬間、すぐにスローイングをさせないように目の前に立つ選手もいなかった。フワッとしたまま3点目を狙いにいき、ワールドクラスのカウンターでやられる。世界では一瞬の隙を与えるだけで、ゴールまで持っていかれることを痛感させられるシーンとなった。